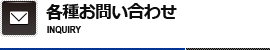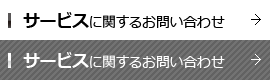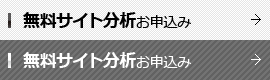富士登山で学べる「セルフコーチング」
投稿者:小川 悟
2007/11/12 09:40
この記事は約8分で読むことができます。
「人間が希望を失わずに生きてゆくためには、どうしても存在しなければならないと作者ドーマルの主張する、この時間空間の原点ともいうべきシンボリックな山の探求の物語」
/『洞窟の偶像』(澁澤龍彦) ~『類推の山』(ルネ・ドーマル)についてのレビュー
昨年9月、同僚に富士登山に誘われた私は、社長や専務、他の同僚たちと富士山へ行きました。
登山自体、小学校時代の遠足以来行ったことのない私にとって、生まれて初めての富士山。登山具店で同僚に勧められたものを少しばかり購入し、高価なものは貸してもらい、それなりの身なりで出掛けました。
当時のことは今でも鮮明に覚えています。なぜなら、情けないことに私は七合目あたりで高山病にかかり、一部始終が苦しい思い出として記憶に焼き付いてしまっているからです。結局、共に登った皆から叱咤激励をもらいつつ、登頂に成功はしたものの、当時は「もう二度と登りたくない」と感じたものでした。
しかし今年8月、私は再び富士登山に出掛けることになりました。
今回も昨年同様、同僚主催のイベントでしたが、社長や専務のほか、取引先の社長様などを含む計12名と、前年の倍の参加者でした。あれほど辛いだけの富士登山に、なぜまた出掛けようとするのか――、登山家の植村直己氏や野口健氏、『日本百名山』を著した深田久弥氏、写真家の田淵行男氏、古くは『富嶽三十六景』をはじめとした浮世絵を描いた葛飾北斎まで山に魅せられた人は多いですが、私にはそこまで高尚な登山に対する動機はありませんでした。「また、みんなで登頂したときの気持ち良さを感じに行きたい」といった感情があるだけで、一人で登りたいとは思いませんでした。
2年連続で3776m(皆なろう)の富士山登頂に成功したのですが、一人ではとても成し遂げられない行為だったと思います。
五合目までは車で向かいます。山頂まではそこからわずか7km超の道のりなのですが、休憩しながら登るので私の足で6、7時間かかりました。下山は下山で、「砂走り」(須走口下山道)が延々と続く砂利道で膝がおかしくなりそうになりました。とにかく、登りのときも下りのときも疲労と酸欠状態に陥り、ほぼ無心状態になっていました。ただひたすらに、「○号目まであと×km」といった標識だけを信じて、「辛いけど、とにかく歩かなきゃ山頂には一生たどり着けないし……」と思いながら歩み続けていました。
今思えば、この富士登山を通じていろいろなことが学べたというか、自分の感性に訴えかけられたように思います。
先の「標識」は仕事にたとえると言わば「マイルストーン(道標)」であり、登頂がプロジェクトのゴール(目標)です。共に登った同僚たちはプロジェクトメンバーです。足への負担を軽減させるために買い求めた金剛杖や、高山病防止のための酸素はツールにでもなりましょうか。
面白いのは、これは私だけの感情かもしれませんが、仲間と共に登っているのですが、精神的・体力的な限界を迎えると、非常に孤独感を覚えるのです。他の人にとっては辛くないのかもしれないが、私には辛い。最悪の事態になっても苦しむのは自分だけだ。こんな辛い思いをするくらいなら、登頂なんてしなくていい、とにかく下山したい――。そんな消極的な感情さえ芽生えてきます。酸欠になり高山病が発症すると、とにかく強度の頭痛と吐き気と眠気に襲われます。仕事のきつさを一気に忘れるくらい、精神的にも体力的にもきつい。
そんなとき同僚が励ましてくれました。代わりに荷物を持ってくれたり、後ろから押してくれたり、酸素を分けてくれたり、追い付くまで待ってくれたり、少しでも楽になる歩き方や呼吸法を教えてくれたり、「休憩地点まであと少しなんだから頑張ろうぜ!」「自分から登頂するって言ったんじゃん」と怒号で叱咤激励されたりetc…。あまりの辛さに、登る前に自分から「登頂したい」と申し出たことをすっかり忘れていたのでした。これすべて仕事に置き換えられるシーンではないかと、このとき感じました。
ここで少し話を脱線させますが、私は学生時代までの一時期、SFや冒険小説(あるいは、ユートピア小説)に分類される本に傾倒していたことがありました。歴史や政治、経済、法律など、まだ社会の一般常識さえもろくに知らない学生時代にあって、何の制約下にもない自身の想像という行為――、たとえそれが何の根拠も目的もない不毛な行為であったとしても――ありもしない理想社会について友人たちと語らうことは至高の楽しみでありました。
そんな私が学生時代に読み、大変感銘を受けた本があります。ルネ・ドーマル(仏,1908-44)が書いた『類推の山』という本です。ドーマルの死後8年を経て、パリのガリマール書店より上梓された小説です。
主人公率いる登山隊は、年齢も職業もバラバラの12名。何を目指して集まったのかというと、この世に存在するかどうかも分からない、けれどもきっとある筈だと仮定されている海の真ん中にある「山」にたどり着くことです。この山を目指して旅に出ようという主人公の誘いにのった人たちの物語です。
ちょうど私たちの職場も、「年齢も(前職の)職業もバラバラ」の新卒社員や中途入社の社員で構成されており、不確かな未来に個々の希望や目標を持って、荒海と化した現実に直面しています。
未完小説として有名な作品なのですが、著者ドーマルの死期が近づいていたある日、病床を訪ねた友人に対して物語が途中となっていた『類推の山』の続きとして最終章に書こうと考えていた「類推の山」の掟についての話を語ったそうです。
「頂上にたどりつくためには、山小屋から山小屋へと登ってゆかなければならない。ところが山小屋をひとつ離れる前に、あとからやってきてその離れた場所に入る人たちのための用意をしておく義務があるんだ。そして、その用意がおわってからでないと、もっと上に登ってゆくことはできない。だから、僕らは新しい山小屋にむかってつきすすむ前に、もういちど下へ降りて、僕らがはじめに得た知識を、別の探索者に教えておかなければならない」
本書でドーマルが私たちに語ろうとしていたのは、まさに”人生”そのものだったのではないかと思っています。
「私は問うた――だが、この「類推的登山」とはいったい何なのか?」
/『類推の山』(ルネ・ドーマル) ~「覚書」より。
よく人生を登山やマラソンにたとえて言うことがありますが、これはそのまま仕事にも当てはまるのではないかと思っています。本書の覚書の中で著者ドーマルは、「高所は低所を知っており、低所は高所を知らない」ということを書いています。高い視点で物事を考えられるようになると、低い視点で考えている人のために「こっちの方が楽だよ」「もっと俯瞰してみるとどうするのがベターか分かるよ」「もう少しだけ頑張ると楽しくなってくるよ」とアドバイスをすることができます。
人生の上でも、仕事の上でも、先駆者が後継者のために自身の知っている知識や手段をマニュアル化したり、経験者がマイルストーン(道標)を立てて注意をひき、迷わせたり挫折させたりしないようマネジメントする必要があります。
それから人は長い人生において、多少の差こそあれ起伏に遭います。目標がひとつ叶えば、また新たな目標ができるものですし、逆に試練をひとつ乗り越えれば、また新たな壁に当たるものです。その度ごとに一喜一憂するような豊かな感性も必要と思いますが、人生を捨ててしまう程に人の道を外したり、落ち込んでしまうことは良くないことだと思っています。ひとつひとつの区切りを認識しながら、同時により高みへ昇ってゆく過程の中にあるということを認識すべきだと私は思います。
本書の内容や、富士登山で芽生えた私の感情は、セルフコーチングになったかもしれません。
自分は本質的にどうしたいのか?どうすればそれを達成できるのか?何が問題・障壁となっているのか?それを解決するための手段は?仲間が辛いときにはどうすればよいのか?辛いと感じている人を放置すると孤独感が増幅する、ゴールまでの距離や道のりを明確にしないと辛さが増す、常に声を掛け合うなど励まし合う姿勢が大切、コミュニケーションの重要性、仲間との協働作業における目標達成時の感動の共有etc…。
仕事に向かう上でモチベーションを維持し続けることは当たり前のことですが、環境によってはそれを阻害する因子も多いことと思います。そういった気持ちのまま社内で影響力を持つ存在になってくると、後から入ってくる人にも伝染してしまいます。できれば良い意味でのインフルエンサー、エヴァンジェリストでありたいものです。そういう風に意識の高い人が増えてくると、マイノリティな存在は減り、逆に帰属意識が高く、自身のミッションを自発的に見つけることができ、それに対して忠実に挑む有能な社員が増えやすくなるのではないかと思います。そうなれば組織はより強固なものとなり、経営者は余計な事で気を揉むことなく、高いレベルでの経営が可能になるのではないかと考えています。
そういった意味で、富士登山はこじつけではなく、様々なことを体感できたイベントでした。
座学では学べない、実践型セルフコーチングとしての富士登山。まだ経験されていない方のためにお勧めします!